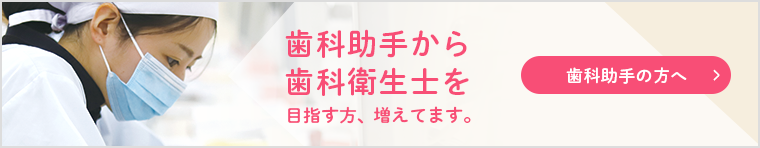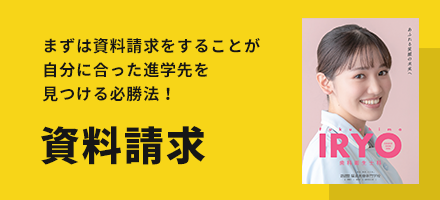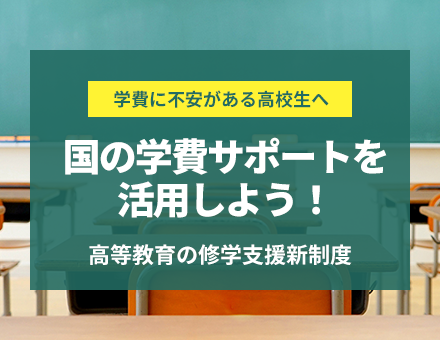歯科衛生士とは
食べる、話す、笑う、
全身の健康を支える
歯科衛生士。

歯と口は、人間にとって特に重要な器官です。食べることや話すこと、笑うことなどは、歯と口が健康に保たれているからこその行為。歯科衛生士は、これらの行為や全身の健康、心身ともに健やかな人生を支える医療の専門職(国家資格)です。口腔内だけではなく、全身の健康を支え、最新の研究では口腔衛生と認知症の関係が話題になるなど、ますます注目を集めています。 やりがいがあり、スキルアップも可能な職業ですが、プライベートと両立しやすく、結婚・出産してからも長く働き続けられるのも魅力のです。
歯科衛生士の三大業務
- ①歯垢や歯石などを除去し
虫歯や歯周病を予防 - ②虫歯の発生と進行を防ぐための
フッ化物の塗布 など
患者さんに直接触れる仕事は、専門の教育と訓練を受け、国家資格を取得した歯科衛生士でなければ行えません。

- ①歯科医師の診療を補助
- ②歯科医師の指示を受け、
治療の一部を担当 など
患者さんが安全で快適な診療を受けるためには、歯科医師と歯科衛生士の綿密な連携が欠かせません。

- ①健康な歯を保つための
正しい歯磨き指導 - ②栄養や食事のとり方の指導 など
乳幼児・児童・成人・障害者、高齢者など、相手に合わせて指導を行います。また幼稚園、小学校、地域の保健センターなどに出掛けて指導することもあります。

歯科衛生士と歯科助手の違い

歯科衛生士と歯科助手(歯科アシスタント)、この2つの職業は似ているようで大きく異なります。
明確な違いは、歯科衛生士は国家資格であり、歯科助手は資格が不要(もしくは民間資格)であるということです。
この違いは業務に大きく影響し、歯科衛生士は患者様に直接処置を行う医療行為や歯科医師の診療補助、歯磨き指導などを中心に行う一方、歯科助手は受付業務や患者様の対応、器具の清掃や準備、カルテ管理や会計事務などの様々な雑務を担当します。業務の違いは給与面、やりがい等の大きな差となります。
また、歯科助手は歯科衛生士と違い、歯科医療をカリキュラムに基づいて学んでいないため、医療事故などの危険性が危ぶまれています。患者様への影響はもちろん、歯科助手自身も医療器具の取り扱いなどにより感染症のリスクなどが危険視されています。
歯科助手からのキャリアアップ
本校の歯科衛生士科は、歯科助手の方が入学するケースが非常に多いのが現状です。歯科助手として歯科医院に勤務する中で、歯科衛生士との業務範囲や待遇面の違いに直面し、歯科衛生士の道を目指す歯科助手が多いためです。実際の入学者に入学した理由を調査すると「受付や事務作業だけでなく治療に携わる仕事がしたい」、「きちんと歯科医療の知識を得たいと思った」、「一生働ける仕事がしたい」、「職場の歯科衛生士に憧れて」、「学費の負担なく資格を取れると知ったから」などの意見がありました。
歯科助手経験がある入学者
社会人入学者(在校生)51人中
歯科助手経験者は32名 約6割が歯科助手!
2022年入学者データより
| 歯科衛生士 | 歯科助手 | |
|---|---|---|
| 業務内容 | (1)歯科診療補助 (2)歯科予防処置 (3)歯科保健指導 ・歯垢や歯石の除去 ・虫歯予防のための処置 ・歯科医師の診療を補助 ・正しい歯磨きの方法、栄養指導など |
歯科医療行為以外の業務 ・受付や電話対応など患者様の対応 ・器具の準備や消毒、院内の清掃 ・カルテ管理、会計事務など |
| 資格 | 国家資格が必要 | 資格は不要(民間資格もある) |
| 資格取得方法 | 厚生労働省指定の養成施設 (専門学校など)を卒業し、国家試験に合格 |
民間資格の場合は各団体の定めによる (数日間の講習や通信講座など様々) |
| 資格の定義 | 歯科衛生士法 第1条、第2条(国が定める) | なし |
| 監督官庁 | 厚生労働省 | なし |
| 修業年数 | 3ヵ年以上 | なし(民間資格を取る場合は数日~1年制) |
| 卒業単位数 | 93単位(2570時間以上) うち臨床実習20単位(900時間) |
法的定めなし |
| 教育内容 | 歯科衛生士学校養成所指定規則による | 法的定めなし |
| 業務内容歯科衛生士名簿に登録 | 厚生労働省により登録 | なし |
※歯科衛生士のみ、患者様の口の中に触れることができます。

仕事とプライベートを
両立しやすい職業。
ほとんどの歯科医院では、日曜出勤・夜勤がなく、プライベートも大切にできます。 また、結婚や出産などで一度現場を離れても、子育てが一段落して職場に復帰したいと考えたときに、育児と仕事を両立させながら再就職しやすい職業でもあります。
歯科衛生士は今後ますます、
世の中に求められる国家資格。
全国で人員が不足していると言われる歯科衛生士ですが、歯科医療のニーズの高まりに伴い、ますます求められる職業となっています。

※2022年12月31日現在の歯科医師数は105,267人(厚生労働省HPより)。 医師1人に対し、2人の歯科衛生士が必要と言われています。

歯科衛生士として、さらなる活躍がしたいという方には、「認定歯科衛生士」の資格取得でキャリアアップが可能です。 「認定歯科衛生士」とは、小児・歯周病・インプラント・介護・福祉・審美・矯正・ホワイトニングなど、特定の専門分野に関する高い知識や技能を持っていると認められた歯科衛生士が取得できる資格です。 また、歯科衛生士の資格を活かして、ケアマネージャーの資格を取得し、福祉の分野へとキャリアチェンジすることも可能です。


海野歯科医院 院長 海野 仁先生
歯科衛生士の活躍の場は広がっています
歯科医療は生きる力を支える生活の医療です。単に技術を提供するに留まらず、患者さんの健康、食生活、会話、笑顔の維持増進のためにあるべきです。このことにこそ歯科衛生士が力を発揮することが期待されています。歯科衛生士の業務範囲は歯科医院の中だけではなく、在宅歯科診療、介護施設、さらには市役所や県庁、保健所などの行政機関での活躍が始まっています。患者さん一人ひとりを勇気づけ、歯と口の健康に注意を向け、人生100年時代の健康長寿に大いに貢献する職業です。
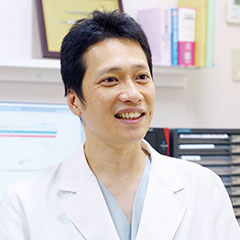
口腔外科 診療科長 口腔機能管理センター センター長
口唇・口蓋・顔面修復センター 副センター長 池谷 進 先生
未来ある若者たちに担ってほしい
歯科衛生士は歯科医師のただのアシスタントではなく、患者さんの口腔機能を医学的に管理する職業です。一人ひとりの口腔内の状況に合わせた管理方法を自ら考え、それを患者さんにわかりやすく説明し、日常生活で実践してもらうことが歯科衛生士の重要な役割です。食べる、話す、飲み込む、味わうなどの口腔機能が失われると誤嚥性肺炎や早産、認知症、糖尿病などの様々な病気を誘発してしまいます。歯科衛生士は国民一人ひとりの健康寿命を守る存在なのです。非常に重要なこの仕事をぜひ未来ある若者たちに担っていただきたいです。